この記事の目次
簡単なあらすじ
第35巻収録。酉の市の人ごみの中で、立て続けに起こった殺人事件。殺された男たちは三年前、岡崎城下でおこった錦織物問屋襲撃事件に関係する者たちだった。捜査が行き詰るなか、殺された男たちの人相書きから事件は急展開する……。
スポンサーリンク
人混みでの殺人事件
鬼平と密偵たちのお出かけ場面から始まる本作だ。年の瀬の浅草での風物詩といえば、酉の市であろう。その酉の市の人混みで起こった殺人事件から展開していくストーリーとなっている。
その殺人事件が起こった理由として鬼平がピンと来たのは、香具師同士の争いが絡んでいるのではないか、という事だった。香具師の元締めと彦十は昔馴染みということで、元締めと面通しをする鬼平。男所帯から供された酒のアテは湯豆腐だ。
元締めは筋を通す男と見抜いた鬼平は、勘働きこそ残念ながら外れてしまうのだが、寒い季節の湯豆腐と酒を堪能出来て満足そうで何よりだ。美味しい湯豆腐は当然、美味しい豆腐あってこそ。果たして近所に出来た豆腐屋の主人と、殺人事件との関連やいかに。
香具師(やし)と的屋(てきや)
本作の舞台となった酉の市なども含め、現代で俗にいう縁日などの出店を管理する者を香具師と呼ぶのだが、元々は“かぐし”と読んでいたそうな。古くは扱う商品や興行の種類によって肩書が異なったそうだが、今では全て総称して香具師や的屋として使われているのだ。
この香具師という言葉、由来は諸説あるが薬を扱っていた事から、薬師、やし、と変化したという説もある。一方の的屋は読んで字の如く、的に関する職業、つまり矢場に関連すると分かってくるぞ。矢場の管理をしていた者が読みの変化によってテキ屋となったようだ。
余談だが、若者が良く使う言葉にヤバイ、がある。嘘か本当かは判断が出来ないのだが、矢場い、が語源との説があり、どうやらテキ屋同士の隠語で使われていたという話もあるのだ。江戸時代の言葉を若者が使い始めるというのも、また面白い現象かもしれないな。
大人気の書物、豆腐百珍
江戸時代には豆腐が庶民にとって一般的な食べ物として広まっていたようだ。そうすると美味しさを追求するのが人の常な訳で、豆腐料理を集めた本、“豆腐百珍”が大人気を博したというのだ。
湯豆腐に関連する豆腐料理も掲載されていて、その中で目を引いたのは湯の代わりに葛湯で豆腐を温める料理だろうか。鬼平が元締めに供された湯豆腐が、その“湯やっこ”なる豆腐料理かは分からないが、湯豆腐を軸に展開されるストーリーだ。豆腐屋を襲う悲劇と、豆腐屋の復讐劇が織りなすストーリーは見ごたえ十分だぞ。
この作品が読める書籍はこちら
滝田 莞爾
最新記事 by 滝田 莞爾 (全て見る)
- 鬼平犯科帳 漫画:第265話『同門の宴』のみどころ - 2022年9月9日
- 鬼平犯科帳 漫画:第48話『おしま金三郎』のみどころ - 2022年9月5日
- 鬼平犯科帳 漫画:第67話『殺しの波紋』のみどころ - 2022年9月1日

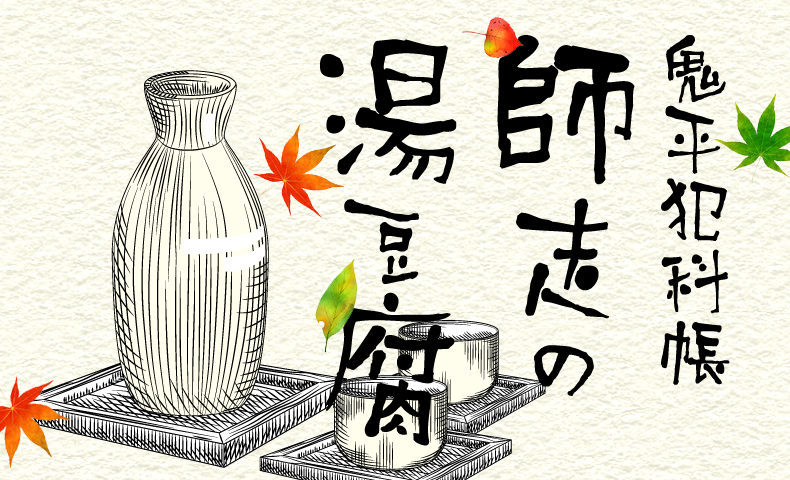







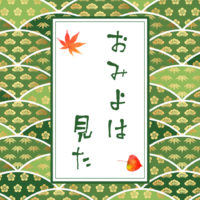



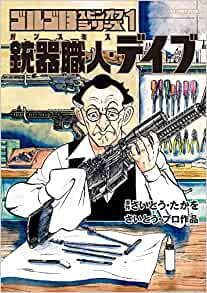
 ゴルゴ13のナビゲートなら当サイトにおまかせ! 自他ともに認めるゴルゴ好きライター陣が、おすすめ作品のみどころを熱く語ります。これであなたもベスト・エピソードに一発アクセス!
ゴルゴ13のナビゲートなら当サイトにおまかせ! 自他ともに認めるゴルゴ好きライター陣が、おすすめ作品のみどころを熱く語ります。これであなたもベスト・エピソードに一発アクセス!






















