この記事の目次
簡単なあらすじ
ワイド版第39巻収録。表御番医師・井上立泉に招かれ、料亭・桔梗屋の蕎麦に舌鼓をうった平蔵夫妻。蕎麦を打ったのは天才職人・おその。じつは、おそのの義弟・弥助が盗賊一味と通じていた。おそのは引き込み女なのか……?
スポンサーリンク
蕎麦打ち名人
鮮やかな手さばきで、あれよあれよと美味しい蕎麦を打っていく蕎麦職人おそのが主役の本作だ。女性ながらに抜群の技量を誇るおそのは、大店に引き抜かれて江戸に来たようだが、その技量はやはり高く評価されているのだな。
この類の話には多くの場合でヒモが付いている事があるのだが、本作ではヒモではなく弟がその役割を担っているぞ。博打で借金を重ねるダメな弟に金の無心を受けるおそのではあったが、まさか自らが働く店への引き込みを懇願されるとは思ってもいなかっただろう。
蕎麦切というタイトルの表現に馴染みの無い方もいるかもしれないが、蕎麦切は蕎麦掻と区別する為の名前と考えると良いだろう。蕎麦はもともと団子状にして蒸して食べていたのだが、江戸時代に蕎麦を麺の形にして食すまでに進化を遂げたのだ。麺の形に切るから“蕎麦切”という訳だな。蕎麦を軸に進んで行く本作は、どうにもお腹が空いてしまうのだ。
江戸の蕎麦
鬼平たちが美味しそうに啜る蕎麦を見て、お腹の空いた読者もいるだろうか。ここでは江戸から続く蕎麦の話をしよう。「藪(やぶ)」「更科(さらしな)」「砂場(すなば)」、江戸から続く蕎麦屋の御三家と言われているな。これらの屋号を掲げる蕎麦屋は、現在でも多く見られるので比較的探しやすいだろう。
地方の方からすると意外に思われるのだが、江戸時代から続く伝統的な蕎麦はつゆが非常に辛いという特徴があるのだ。ここで言う辛いとは、唐辛子などのホットという意味ではなく、”塩っ辛い”の辛いだと考えてほしい。例えば刺身を醤油につけて食べる時、端っこをちょこんと醤油につけて食べる方が多いだろう。
江戸の蕎麦も非常に近い食べ方だぞ。蕎麦を箸で持って、蕎麦の端っこをつゆに少しだけつけて食べるのだ。間違ってもつゆに蕎麦を浸してしまったら、辛くてとても食べられた物ではないぞ。ぜひとも粋な蕎麦を味わってほしいのだ。
虎狼痢(コレラ)の猛威
おそのの故郷が虎狼痢に襲われ、その結果で家族が不幸に見舞われたという描写がある。ここでいう虎狼痢とはコレラという感染症の事だな。江戸時代に限らず、現代医学が普及する以前の世界は感染症との戦いであったと言っても過言ではないだろう。
コレラはもちろんの事、天然痘(疱瘡)や梅毒、らい病、結核などの感染症も江戸時代では猛威を振るっていたのだ。コレラは重度の脱水症状を引き起こす感染症なのだが、特徴的な症状としては米のとぎ汁様の下痢が挙げられるだろうか。我々は大腸という部分で多くの水分を吸収するのだが、コレラ菌の出す毒素によって逆に大腸から水分が放出されてしまう事が原因なのだ。
現代でこそ失われた水分を補給する対処法が正しいと言えるのだろうが、水分を補給する方法が口から飲ます以外になかった時代だ。当時の医学においてはどう対処をして良いのか見当も付かなったと思うのだ。今でこそ大した事の無い感染症と思われている物でも、当時の人々にとっては、それはそれは恐ろしい物だったろう。医学の発展には感謝したいものだな。
この作品が読める書籍はこちら
滝田 莞爾
最新記事 by 滝田 莞爾 (全て見る)
- 鬼平犯科帳 漫画:第265話『同門の宴』のみどころ - 2022年9月9日
- 鬼平犯科帳 漫画:第48話『おしま金三郎』のみどころ - 2022年9月5日
- 鬼平犯科帳 漫画:第67話『殺しの波紋』のみどころ - 2022年9月1日

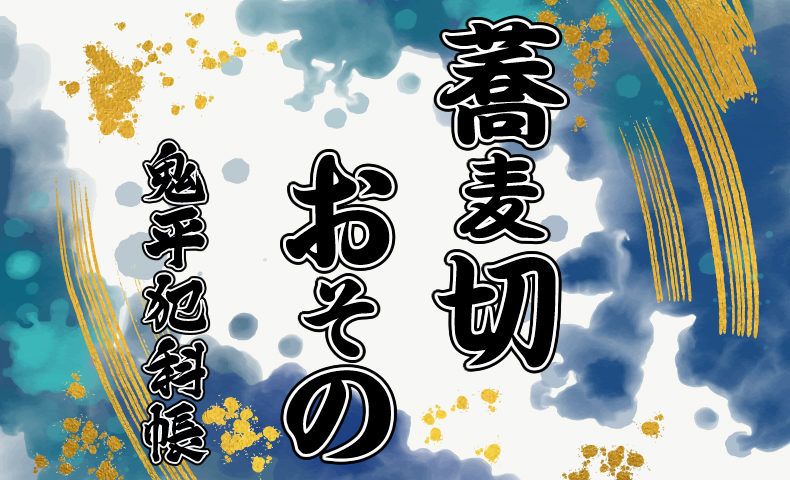

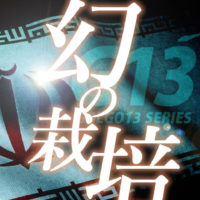



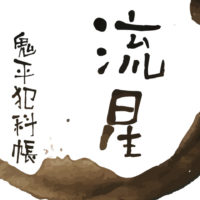





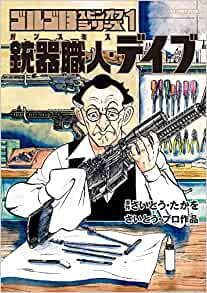
 ゴルゴ13のナビゲートなら当サイトにおまかせ! 自他ともに認めるゴルゴ好きライター陣が、おすすめ作品のみどころを熱く語ります。これであなたもベスト・エピソードに一発アクセス!
ゴルゴ13のナビゲートなら当サイトにおまかせ! 自他ともに認めるゴルゴ好きライター陣が、おすすめ作品のみどころを熱く語ります。これであなたもベスト・エピソードに一発アクセス!






















